体重の急激な変化が原因

妊娠して6ヶ月目くらいから腰痛を訴える人が大半です。その原因は体重の急激な変化です。しかし出産の後も腰痛に悩まされる人も大勢います。
これから登場していただく若いママさんも妊娠して6ヶ月くらいから腰痛を感じるようになったと言います。これは体重の急激な増加が原因だから、出産が終われば腰痛から解放されるだろうと期待していたと言います。
しかし期待とは裏腹に腰痛は収まりません。そこで療術師のもとを訪ねました。その時のこの若いママさんと療術師の会話を再現します。この会話から出産後の腰痛の原因と対策を考えていきたいと思います。
初産後一カ月余り経過した27歳:妊娠して6ヶ月くらいから腰痛を感じるようになる。現在授乳中のため薬は使用せずに腰痛を治したい。
「妊娠してから、特に6ケ月目に入ったごろから腰が痛くなりました」
・・腰痛の原因は何か思い当たりますか・・
「直接のきっかけはありませんでした。徐々に痛くなってきましたから」
・・妊娠中にはどれくらい体重が増えましたか・・
「8キロほど増えました」
・・じゃあ、妊娠中に急激に体重が増えたのが原因でしょう。何しろ、今までより急に8キロも増えたのですから。それで腰の負担が増えたのでしょう・・
「そうですが」
・・女の人の身体は、出産時には、陣痛と共に骨盤の関節(仙腸関節)も緩んで約5センチ開いてくるのです。生み終えるとまた関節は閉じてゆきます。
妊娠中、腰痛になったり、産後、腰痛になる人はこの関節がスムーズに動かなかったり、元の位置に収まるのが少し失敗した人なのです。よく産後の「ひだち」が悪いと言う人もいます。そんな人は殆ど骨盤に歪みが生じていますよ・・
「私の場合もそうですか」
・・恐らくそうでしょうが、心配には及びません・・
患者さんと療術師の会話で理解できたと思いますが、産後の腰痛の原因は殆どの場合、股関節の歪みなのです。
ここで実際の診断の模様を再現します。
骨盤の土台は股関節: その歪みを見つける方法 テスト№1)
1)上向きに足を伸ばして寝る。そして膝頭を合せて直角に立てる。
2療術師は)膝頭から大腿部(太もも))前面が胸に着くように片方ずつ胸に押しつけてみる。
3)このテストで右足と左足では、どちらが胸に着き難いかを確認する。
4)着き難い方の股関節の歪みが大きい。
もう一度、患者さんと療術師の会話の再現です。
・・右と左ではどちらが着き難いですか?・・
「はい、右膝を押されてもどうもないのですが、左膝では腰に響いてきます」
・・これが歪みなのですよ。殆ど人は腰が悪いとそこだけで、他の部分は全く正常だと思っています。しかし原因のない結果はありません・・
療術師の診断方法:患者さんの開脚ポーズから診断。
骨盤の土台は股関節: その歪みを見つける方法 テスト№2
1)足(脚)を伸ばして座る。
2)足(脚)を左右に開脚のポーズで開きます。
3)左右の足(脚)で開き方を比べてみて、どちらが開き難いかを確認する。
4)開き難い方が股関節の歪みが大きい。
・・この様に左右で差が出来て、上半身の体重が左右の股関節に掛った場合、例えば60キロの人では、左に33キロ、右の27キロというように偏ります。
繰り返しますが股関節は骨盤の土台ですから、ここが歪んできますと、股関節の上に乗る腰が安定しません。負担がかかるのです。だからこの股関節から修正しないとダメなのです・・
ここからは療術師の診断方法を応用しながら、一人で出来るストレッチを紹介します。

股関節の歪みを修復するストレッチ
1)足(脚)を伸ばして寝る。
2)右の足の膝を立てる。その膝を両手で抱えて、膝から大腿部(太もも)の前面が胸に着くように引きつける。
3) 右の足の膝を立てて、その膝を両手で抱えて、膝から大腿部(太もも)の前面を身体の外側に倒す。
4) 右の足の膝を立てて、その膝を両手で抱えて、膝から大腿部(太もも)の前面を身体の内側に倒す。
5)この胸の方向、外の方向、内の方向と三方向に倒してみて、一番、倒れやすい方を確認する。
6)左足も右足と同じやり方で、同じ動作をする。一番、倒れやすい方を確認する。
倒しやすい方の足をストレッチする: 倒れにくい方はそのままで何もしない!
1) 上向きに足を伸ばして寝る。
2)右足の膝を立てて、その膝を両手で抱えて、倒しやすい方に倒し切る。そこで止める。足は元の姿勢に伸ばそうとする。両手は足の動きに逆らってそれを妨げようとする。そのまま数秒間押し合いをして動きを止める。その後、両手の力を一度に抜いて足をパッと開放して脱力する。この動作を5から10回繰り返す。
3)左足も右足と同じやり方で、同じ動作をする。
□倒し難い方ではありません。倒しやすい方をストレッチするのです。間違わないで下さい。間違うと効果がありません。
□最初はぎこちなくても読み還しながら、繰り返すうちに、上手くなります。習慣になるとより効果が出ます。

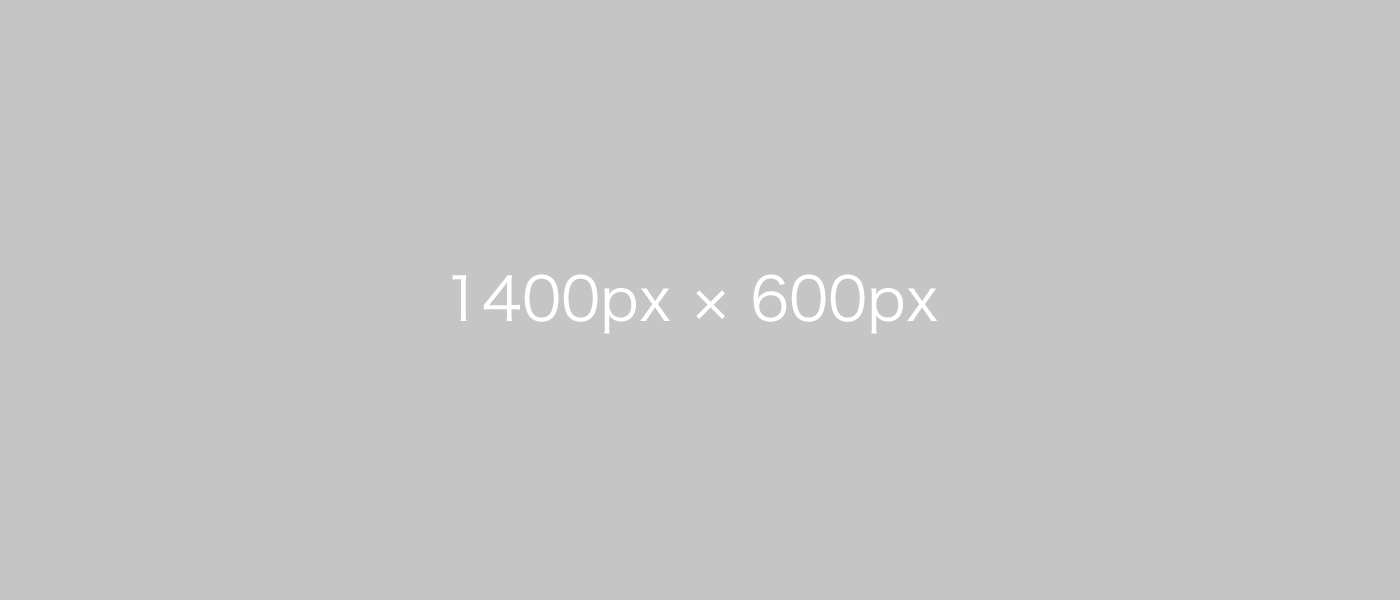
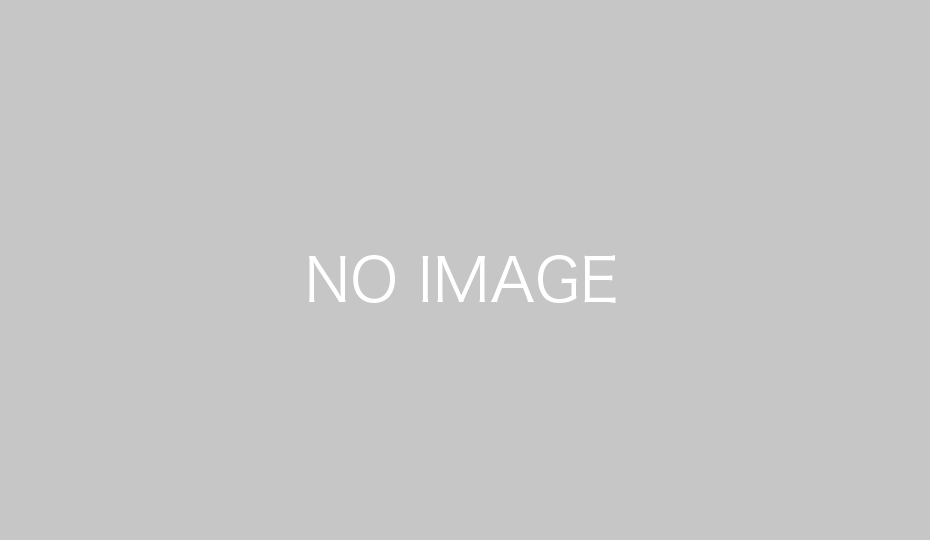
コメント